2025年ドイツの流行語大賞 Das Wort des Jahres 2025
あけましておめでとうございます、2026年の幕開けです。
毎年恒例となって参りましたが、今年もまずはドイツ語協会(GfdS)が選んだ2025年のドイツの流行語大賞についてお伝えします。(2024年の流行語大賞、2023年の流行語大賞)
2025年もドイツは政治的にも社会的にも多くの課題を抱えていましたが、同時にテクノロジーの進化が社会を大きく変えた1年でもありました。
それは流行語にも表れています。

あけましておめでとうございます、2026年の幕開けです。
毎年恒例となって参りましたが、今年もまずはドイツ語協会(GfdS)が選んだ2025年のドイツの流行語大賞についてお伝えします。(2024年の流行語大賞、2023年の流行語大賞)
2025年もドイツは政治的にも社会的にも多くの課題を抱えていましたが、同時にテクノロジーの進化が社会を大きく変えた1年でもありました。
それは流行語にも表れています。

皆様こんにちは。
今日は地域変種からは少し離れますが、ドイツ語の中でも基本文法として学ぶ、二人称Sieとduにまつわるドイツ語の機微に触れていきたいと思います。
この二つの二人称は私たちがドイツ語を学ぶときに、日本語の敬語と比較されながら勉強することが多いと思います。
「敬語はSie」と覚えた方も多いのではないでしょうか。
確かにその解釈は間違っていないのですが、場合によってはその解釈のまま一貫してSieを使い続けると距離を取られている、もっと言ってしまうと感じが悪いと話し相手に受け取られることもあり得るのです。
実はドイツ語ネイティブの人々も、日々の会話の中でSieとduの選択に迫られ、話し相手といわば交渉していると言えます。
今日はそんなSieとduの「敬語か友達との会話か」以上のコミュニケーション上の事情を見ていきたいと思います。

皆様こんにちは。
少しお休みをいただきリフレッシュをしていたところ、急きょまたドイツ西部に戻ることになりました。
なのでこれからはまたドイツ西部のお話もしていきたいと思います。
乞うご期待!

皆様こんにちは。南ヨーロッパでは40度を超えた地域もあり、ドイツもしばらく暑い日が続きましたが、急に気温が下がりお天気も不安定になりました。
気候変動をひしひしと感じます。日本は猛暑が続くようですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
さて、今回のテーマは発音に関するちょっとしたお話をしたいと思います。
ドイツ語を学習する際に「ドイツ語は発音のルールも比較的固定されるし、例外もないから学びやすい」と言われることがあるかと思います。
実際、英語やフランス語に比べればドイツ語のスペルと発音の関係性は比較的学びやすく、覚えやすいものが多いというのが、私が初学者の頃に感じたものでした。
そんな風に感じながら学習歴を数年重ね、当時タンデムパートナーであった夫とタンデムをしていた学生時代。
とある単語の発音について笑われるという出来事がありました。それが„Birne“の発音だったのです。
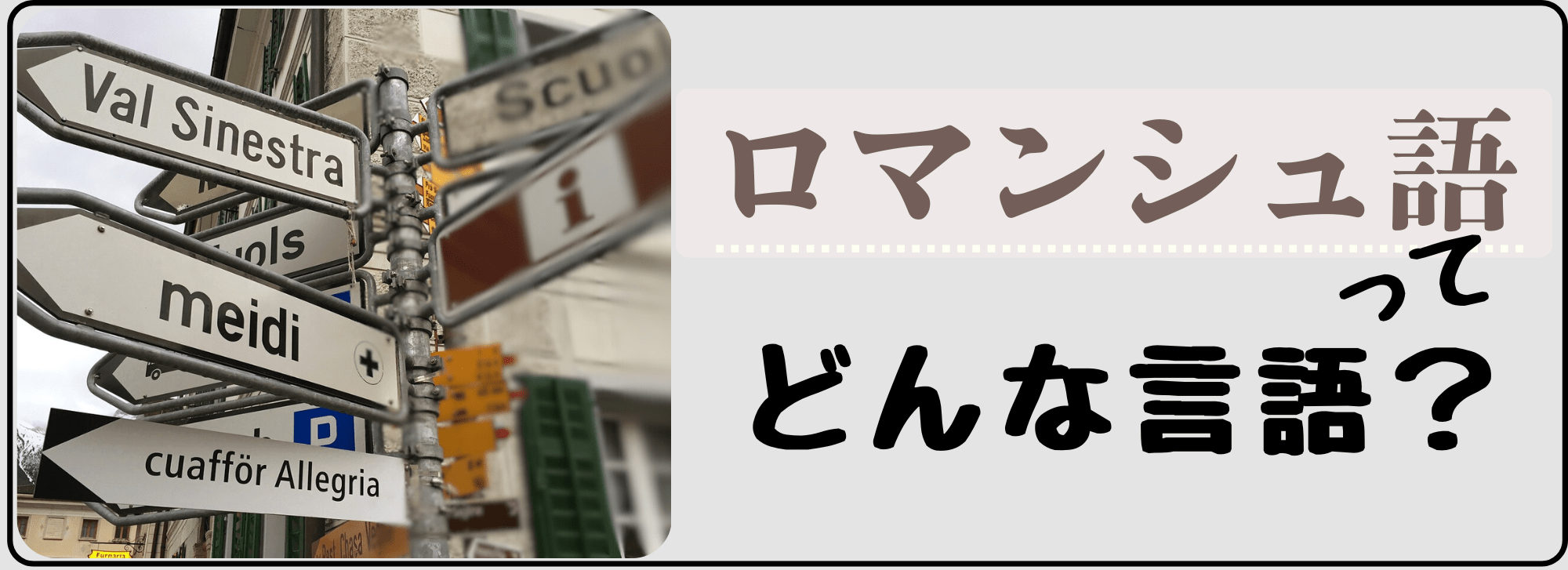
本ブログでは今まで何度かにわたってスイスにドイツ語、フランス語、イタリア語およびロマンシュ語という4つの公用語があることに触れてきました。
日本の皆様からすれば公用語がいくつもあること自体が既に不思議な状況であるだけでなく、その内訳についても違和感を抱く人が少なくありません。
というのも、ドイツ語、フランス語、イタリア語に関してはメジャーな言語であることからよくご存知である一方、4カ国語目のロマンシュ語は殆どの人がまず耳にすることのない詳細不明の言語だからです。
そのため、読者の中にも過去の記事で登場した際に「ロマンシュ語ってそもそも何?」と、思った方が多いのではないでしょうか?
そこで、今回はスイスの第4公用語でありながらも、世界の大半にとって得体の知れないロマンシュ語について色々とご説明させていただきます。

前回はお休みを頂きました。南ドイツはまだまだところどころ寒い日もありますが、それでも春に向かっているような空気を感じます。季節の変わり目ではありますが皆様いかがお過ごしでしょうか。
今回は発音にフォーカスしたテーマでお送りしたいと思います。
突然マニアックに聞こえるかもしれない質問からスタートしますが、皆様にはドイツ語に限らず好きな発音はありますか?(好き、というと抽象的すぎるかもしれませんが。)
「この発音は自分にとってはドイツ語らしく聞こえて好き」だったり、「フランス語の多様な鼻音が好き」だったり、「好き」の判断基準は様々だと思います。
私がとりわけドイツ語の中で好き、というか非常に興味を強く感じる発音はタイトルにもあるとおり、例えばドイツ語の一人称単数主格のichや、形容詞schwierig、前置詞のdurchなどに見られる、ドイツ語のつづりで言えば“g”または“ch”の発音です。
そもそもヨーロッパの言語の中に見られる各口蓋垂の発音分布と各言語間における関係性は、私が大学で音声学や音韻論を学んだ時にそのバリエーションや推移についてロジカルだなあと感じることが多々ありました。
そして特にドイツ語における発音に対する関心がとりわけ強まり、日々観察するようになったのが、ドイツで生活を始めてから、もっと言えば南ドイツに引っ越してきてからでした。
今日は関連する発音のバリエーションについて取り上げたいと思います。
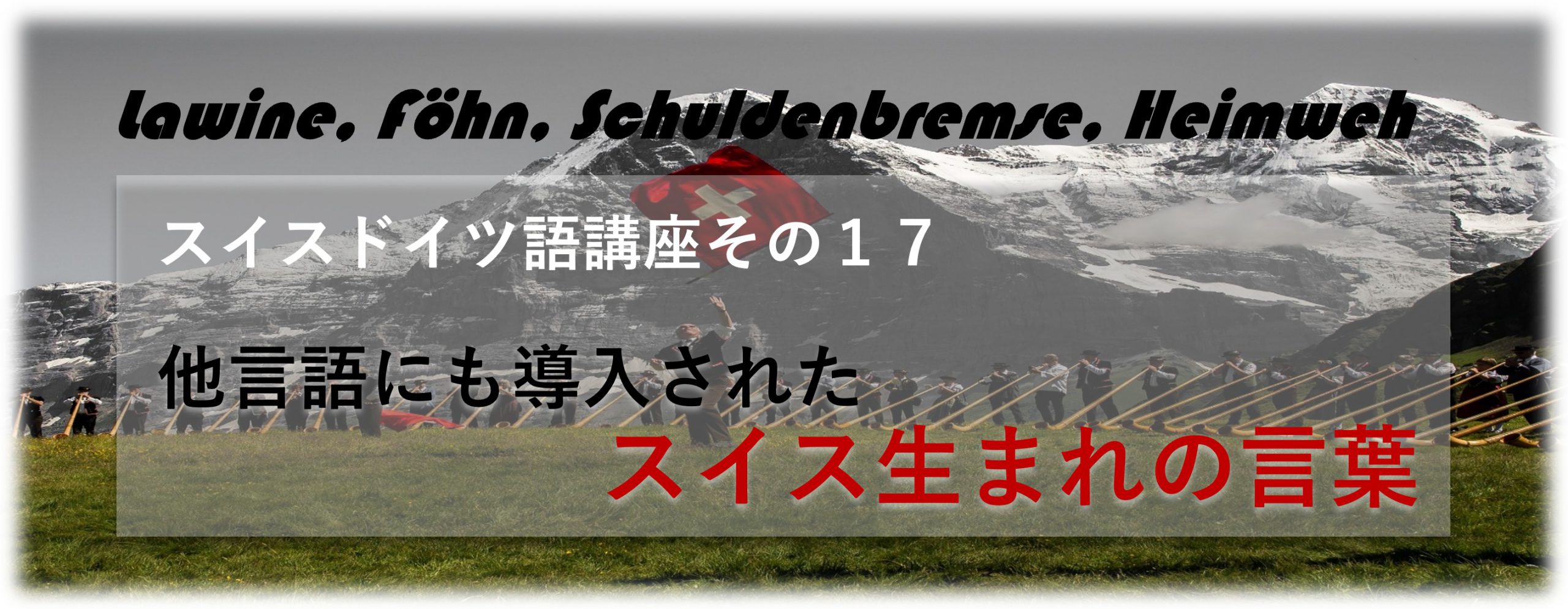
今までのスイスドイツ語講座では、主に標準ドイツ語に対してスイスドイツ語にはどのような違いがあるのかを示してきたことが多かったかと思います。
スイスドイツ語はアレマン語に属するドイツ語の方言のひとつであることから、標準ドイツ語を基に異なる点をご説明するのは決して間違っていません。
しかし、スイスドイツ語は独自の発展を遂げたドイツ語のバリエーションであるため、標準ドイツ語が必ずしもその語源となっている訳ではないのです。
例を挙げるとすれば、過去の記事でも何度か登場したフランス語を始め、他の言語に由来する表現などがありましたよね?
それ以外にも、スイスはドイツ語圏に含まれるものの、地理、地質および気候といった自然はもちろんのこと、文化や政治においてもドイツやオーストリアとは異なる点が多いです。
それらの要素も長い歴史の中で言語に影響を与えてきましたので、スイスドイツ語だけに存在し、標準ドイツ語にはない独自の単語や表現も少なくありません。
そして、その一部はなんと時間の経過とともに標準ドイツ語をはじめ、様々な言語にもわたりました。
したがって、今回はそんなスイス発祥で、いわゆる「逆輸入版」としてドイツ語圏全域やその他の言語にまで広がった言葉をご紹介させていただきます。
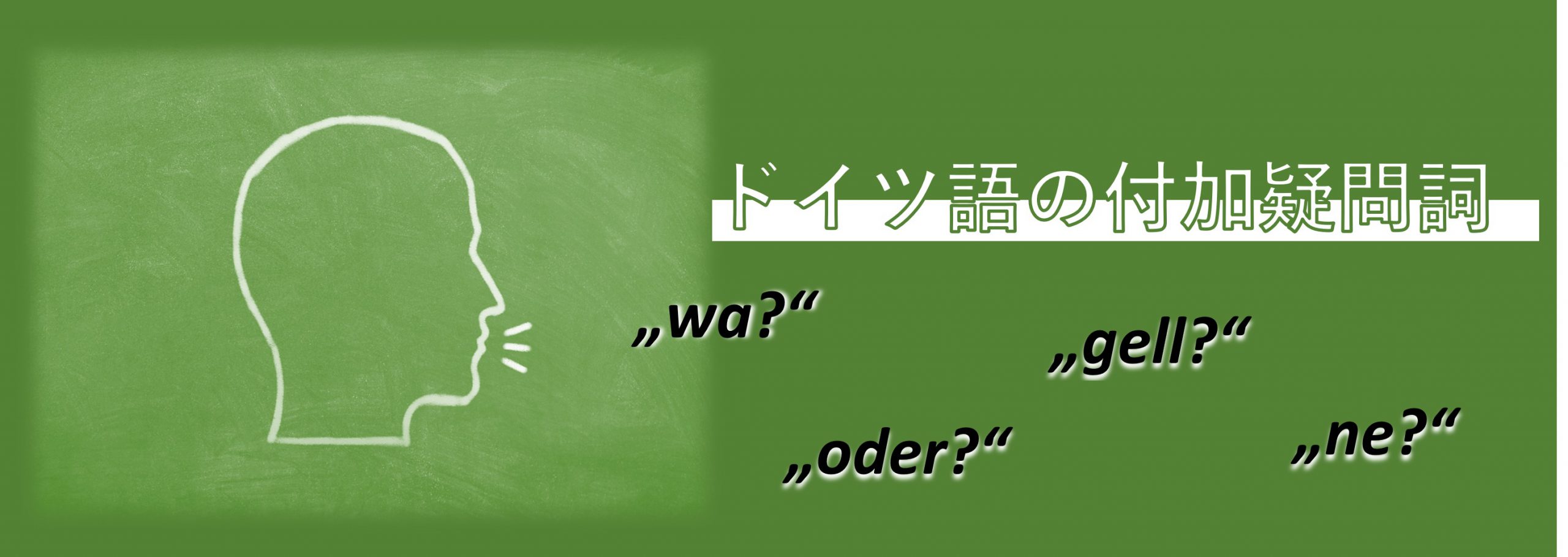
こんにちは。皆様素敵なクリスマスを過ごされたでしょうか?
このブログも今年の夏に書き始めて第四回目を迎えることとなりました。
私のドイツ語をめぐる経験談を、専門であるドイツ語諸言語学の観点から専門的になりすぎないくらいに記事として書き、興味をお持ちの皆様にこうしてお伝えするのはとても楽しく、読んでくださった知り合いの方々からも「これからも楽しみにしているよ!」と、たくさんの温かい声をかけていただいております。本当に励みになります。ありがとうございます。

あけましておめでとうございます、2025年の幕開けです。
毎年恒例となって参りましたが、今年もまずはドイツ語協会(GfdS)が選んだ2024年のドイツの流行語大賞についてお伝えします。(2023年の流行語大賞、2022年の流行語大賞)2024年もドイツは政治的にも社会的にも多くの課題を抱えていました。それは流行語にも表れています。

こんにちは。第三回目となる今回もドイツ語の多様性、とりわけ口語の豊かさの一つである二重完了形(ドイツ語:Doppelperfekt, Ultra-Perfekt)をテーマに、私の経験を交えてお伝えしたいと思います。
ドイツ語学習者の皆さんの多くは、ドイツ語の文法のうち時制について学んだ際に、「ドイツ語では、過去のことを話す時には現在完了形で表現する」と言われているのではないでしょうか。
私個人としては少々一般化しすぎた言い方なのではないか、と思うところはあり、過去形の出番が全くないわけではないので、是非学習者の皆様には過去形も一緒に覚えてもらいたいと願っているのですが、確かにドイツ人の方と「昨日こんなことがあってさー」なんていうおしゃべりをする際に、現在完了形の出番が非常に多いのは事実です。
逆に言えば、学習者である私たちが、この現在完了形をマスターすることができれば、ネイティブの人との会話の幅が広がり、ドイツ語を使う楽しみが増える、そんな文法事項であるとも言えるでしょう。
私がドイツで生活を始めて数ヶ月が経った頃、ドイツ語での会話には完全に慣れ、文法を気にしながら話すというよりは、むしろ会話の場や文脈に適した語彙選びの方に気が向くようになっていくという時期を迎えました。
その頃の私は「文法事項はもう問題ないし、分からないことはなくなったな」と、文法に関しては大きな自信を持っていました。
しかし、ドイツへ来て初めて聞いた上に、相当な頻度で会話の中に見られる文法事項を前にその自信は打ち砕かれます。