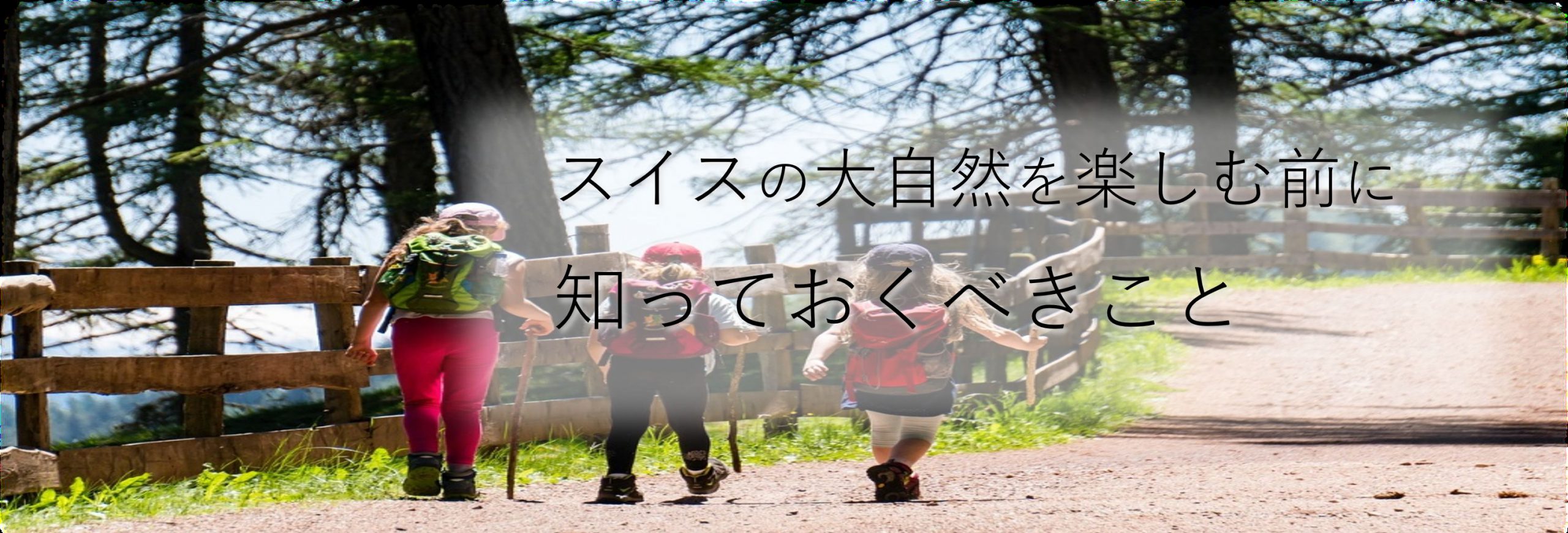
スイスの大自然を楽しむ前に知っておくべきこと
Table of Contents
日本では殆どの場所で桜のシーズンが終了し、春真っただ中で過ごしやすい気温になりましたね。
スイスでも5月に入るとかなり温かくなって、草原が様々な植物で色鮮やかに埋め尽くされる時期です。
そのため、私自身がスイスの自然を楽しむために最も好きなのがこの季節で、外国人に対してもスイスを5月~6月に訪問することをお勧めしています。
特に、ハイキングが趣味という方はあらゆる所で、新緑や高山植物の数々を目の当たりにできますのでアルプスの美しさを満喫するにはうってつけです。
そんな春のスイスは絵にも描けないほど綺麗ですが、自然に関する最低限の知識を持っていないと厄介な目に遭う危険も潜んでいます。
例えば、春になるとキャンプ場などで冬眠から目覚めた腹ペコな熊がウロウロしていて、細心の注意を呼び掛けていますよね?
幸か不幸かスイスでは熊が120年以上前に絶滅したため、稀にイタリアから国境を超えてやってくる例外を除けば、熊に遭遇する恐れはまずございません。
しかし、自然界で注意しなくてはならないものは猛獣だけではなく、むしろ小さくて見落としがちだけど人間に相当な被害を加える可能性を秘めている動植物に気を付けなくてはいけません。
そこで、今回は皆様が安心してスイスの自然を楽しめるように、事前に知っておくべき情報をご紹介させていただきます。
様々な感染症の病原体を伝播するマダニ
スイスの自然において最も注意が必要なのは何と言ってもマダニです。
マダニは日本にも数種類生息していることから既にご存知の方も多いと思いますが、主に哺乳類を宿主にして血液を採取するダニ目に属する寄生虫を指します。
人間から血液を吸血する習性に関しては蚊とさほど変わらないものの、吸血行為に際して様々な細菌やウイルスを宿主に伝播する可能性がある点で大きく異なるので用心しなくてはなりません。
マダニは宿主の皮膚を切り裂いて皮下の血液を摂取するため、一般的に膝窩、股間、耳の後ろ、ならびに髪の毛の生え際といった皮膚が極端に薄い部位を狙います。
したがって、一瞬の不注意だけで血を吸われる確率は低い他、血液を吸われたとしても病原体を確実に伝播されるとは限りません。
また、病原体にも発症率があって、マダニに嚙まれたから必ず感染症に掛かる訳ではありませんし、早めに医師に診てもらって適切に治療すれば大事に至ることも基本的にないです。
とはいえ、マダニが媒介する細菌やウイルスにはかなりの種類が存在し、中には僅かながら死亡例まで報告されているQ熱、ライム病、野兎病、ダニ媒介性脳炎、および重症熱性血小板減少症候群を引き起こすものもいます。
そのため、日本では国立感染症研究所や厚生労働省が全国規模で注意を呼び掛けており、スイスでも政府や地方自治体がマダニの危険性を周知していると共に、感染症を媒介された患者の報告例を基にマダニハザードマップを作成するなどの対策を講じているのが現状です。
そんなスイスにおいて一番多く見かけるマダニの種類はリシヌスマダニ(学名:Ixodes ricinus)で、3月頃から11月に掛けて標高2000メートルまでの草むらがある場所ならほぼどこにでもいます。
そして、リシヌスマダニが最も頻繁に伝播する病原体には複数の臓器に影響を及ぼし、慢性関節炎や慢性脳脊髄炎に発展するライム病を引き起こすボレリア菌(学名:Borrelia burgdorferi sensu lato)に加え、治療しても神経学的後遺症が残る場合があるダニ媒介性脳炎の原因となるフラビウイルスの仲間(学名:Orthoflavivirus encephalitidis)が挙げられます。
それ以外にもマダニによって媒介される病原体がございますが、何れにしても感染を防ぐのが好ましいので、春から秋に向けてスイスの大自然を楽しみたい方は肌の露出を避け、袖口と裾の隙間を無くす服装を着用したり、忌避剤を用意したりしてそれなりの予防措置を取ることが必須です。
さらに、森林や草むらを歩いた後にマダニが自分の身体に飛び移っていないかをこまめに確認し、発見したらすぐに払い落とすと、通常は被害に遭うことは殆どありませんので皆様もそれを念頭に置いて自然をご堪能ください。

他の蟻とは訳が違うヨーロッパアカヤマアリ
続いて、マダニほど危険ではございませんが、スイスでの自然を満喫するにあたって気を付けないといけないもうひとつの存在として、ヨーロッパアカヤマアリ(学名:Formica rufa)があります。
ここで「蟻」と聞いて、「は?」と思った方もいるのではないでしょうか?
確かに、我々が日常生活において街中の公園で目にする蟻は特に警戒する必要がないおとなしい生き物です。
しかし、蟻の仲間には近年アレルギー反応や蕁麻疹等の症状を引き起こし、アナフィラキシーショックによって命の危険にさらされるもあることで話題になったヒアリ(学名:Solenopsis invicta)も存在するため、種類によっては注意を要します。
北極圏に近い北欧北部や地中海の沿岸部を除いてヨーロッパ全土ならびにロシアに広く分布し、スイス国内でも頻繁に目撃するヨーロッパアカヤマアリもまた決して侮ってはいけない蟻の一種です。
ヨーロッパアカヤマアリはヒアリほどの危険性はないものの、警戒心が非常に強く、それらの巣または活動範囲に入ると相手が何倍も大きい人間であっても攻撃してきます。
そして、その攻撃というのは相手の皮膚を噛んで、傷口に毒を注入する方式です。
注入される毒は蜂ならびに海月も自身を守る際に使用する「ギ酸」で、数時間にわたってひりひりする刺激的な痛みをもたらします。
体質によってはギ酸と接触した部分が腫れたり、その他の皮膚反応が出たりするものの、命の危険性はありません。
また、ヨーロッパアカヤマアリは相手に直接触れなくても15センチまでの距離なら何とギ酸を相手に向かって噴射することもできるので、近くにいるだけで攻撃される可能性があります。
したがって、ハイキングなどで山道または森林を移動している時は特に注意を払う必要はないのですが、道中で休憩する際は休憩場所が蟻の縄張りでないことを必ず確認するようにしてください。

触れると厄介なイラクサ
さて、これまでスイスの大自然に潜む要注意動物を2種ご紹介させていただきましたが、警戒が必要な生物には動物ばかりではなく、植物も含まれます。
植物の中には毒性を持ち、摂取すると僅かな量でも人間に至らしめる危険性を有するものが存在することは言うまでもありません。
そして、アルプスにも美しい青紫色の花が目を引くけど実は猛毒のヨウシュトリカブト(学名:Aconitum napellus)など複数の有毒植物が自生しています。
また、人間にとって直接脅威にはならないものの、ムシトリスミレ(学名:Pinguicula vulgaris)やその仲間であるアルプスの在来種(学名:Pinguicula alpina)といった食虫植物もございますので、ハイキングの際に見かける植物に関してはむやみに触ったり、摘採したりせず、鑑賞程度に楽しむようにしましょう。
とはいえ、スイスの自然には例え観賞目的であっても、発見したらとにかく近づかない方が身のためである植物がひとつだけあります。
その植物とは日本にもいくつかの種類が分布している「イラクサ」です。
イラクサは漢字で「刺草」と表記され、学名の由来とのなったラテン語も「燃える」を意味することから、その名前が既に危険な匂いを感じさせます。
具体的に何が危険かと言うと、イラクサは鹿などの外敵から身を守るため、葉と茎に高密度に配置された刺毛を有し、それらの刺毛は軽く触れただけでも皮膚に刺さると同時に発痛物質が皮下に注入されるのです。
この発痛物質の内容はまだ完全に解明されていないものの、ギ酸の他に、ヒスタミン、アセチルコリン、セロトニンが含まれていることが分かっています。
そのため、刺毛に触れた瞬間、注射針が刺さったような痛みが生じ、その後数時間継続する燃えるような刺激に加え、強い痒みを伴う膨疹などの皮膚症状を引き起こすことも多いです。
スイス国内で確認されているイラクサはセイヨウイラクサ(学名:Urtica dioica)とヒメイラクサ(学名:Urtica urens)の2種類のみですが、そのどちらも触れると上記の症状が出ます。
さらに、前者に関しては標高が高い所を除いて草原や森林、街中のあらゆる場所に自生しているので、半ズボンで林道または茂みを通ると高確率で接触してしまう可能性があります。
したがって、スイスで生活している人なら誰しもが最低1度はイラクサの被害に遭ったことがあり、同じ経験をする観光客も少なくないのが現状です。
幸いにも重症化することはありませんが、スイスの自然を満喫する計画が蕁麻疹で台無しにならないよう、皆様もイラクサには十分気を付けることをお勧めします。

今回は「スイスの大自然を楽しむ前に知っておくべきこと」と題してスイスの自然で特に注意すべき動植物について色々とお話をさせていただきました。
見方によっては読者の恐怖を煽る内容だったかもしれませんが、ご紹介したものは何れも皆様がなるべく被害に遭わず、スイスでの滞在をより楽しく過ごせるためのアドバイスとしてご提供いたしましたので、怖がらせる意図は一切ございません。
逆に、日本では「ハブ」に遭遇したり、海水浴場で海月に刺されたりする可能性がありますので、それに比べたらスイスの自然に潜む危険は大したことがないと言えます。
また、昨年の10月にJOJOさんが「ドイツの森歩き」でも言及したように、ドイツ、そしてスイスでも森に行けば「旬の味覚がタダで楽しめる」ことから、自然は怖い要素よりも楽しくて嬉しいことの方が圧倒的に多いです。
私自身もスイスに住んでいた頃はよくラズベリーやブラックベリー、ワイルドストロベリーなどを採りに行き、たまたま車で通った山道で美味しそうなものを発見しては一時停車してそれらを採取しました。
そういう意味で、皆様もスイスの自然で注意を要する危険に気を付けながら、日本ではなかなか味わえない楽しみ方を見つけてください。
では
Bis zum nöchschte mal!
Birewegge
今回の対訳用語集
| 日本語 | 標準ドイツ語 | スイスドイツ語 |
| 外国人 | Ausländer
(アウスレンダー) |
Usländer
(ウスレンデル) |
| 絶滅する | aussterben
(アウスシュテアーベン) |
uusschterbe
(ウースシュテルベ) |
| 皮膚 | Haut
(ハウト) |
Huut
(フート) |
| 関節炎 | Gelenkentzündung
(ゲレンクエントツュンドゥング) |
Glänkentzündig
(グレンクエントツュンディク) |
| 裾 | Hosensaum
(ホーセンサウム) |
Hosesuum
(ホセスーム) |
| 蟻 | Ameise
(アーマイセ) |
Ameisi
(アーマイスィ) |
| ギ酸 | Ameisensäure
(アーマイセンソイレ) |
Ameisesüüri
(アーマイセスューリ) |
| 花 | Blume
(ブルーメ) |
Blueme
(ブルエメ) |
| イラクサ | Brennnessel
(ブレンネッセル) |
Brännnessle
(ブレンネッスレ) |
| 蕁麻疹 | Nesselausschlag
(ネッセルアウスシュラーク) |
Nesseluusschlag
(ネッセルウースシュラーク) |
参考ホームページ
スイス連邦健康庁:マダニによって媒介する疾病:https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/krankheiten-im-ueberblick/zeckenuebertragene-krankheiten.html
スイス連邦環境庁:森に住む甘党ヨーロッパアカヤマアリ:https://www.wald-vielfalt.ch/walderlebnis/rote-waldameise/detail
スイス連邦環境庁:ヨーロッパアカヤマアリは本当におしっこができるのか?:https://www.wald-vielfalt.ch/walderlebnis/rote-waldameise
スイスアレルギーセンター:植物によって皮膚が刺激されると:https://www.aha.ch/aktuelles/wenn-pflanzen-haut-reizen
コンコルディア健康保険:幼児がイラクサと接触した場合:https://www.concordia.ch/de/schwangerschaft-und-eltern-sein/mein-baby-ist-krank/brennnesselkontakt.html

スイス生まれスイス育ち。チューリッヒ大学卒業後、日本を訪れた際に心を打たれ、日本に移住。趣味は観光地巡りとグルメツアー。好きな食べ物はラーメンとスイーツ。「ちょっと知りたいスイス」のブログを担当することになり、スイスの魅力をお伝えできればと思っておりますので皆様のご感想やご意見などをいただければ嬉しいです。

Comments
(0 Comments)