ドイツのサラダ フェルトザラート
ドイツで暮らしていると、スーパーや市場でよく見かける「Feldsalat(フェルトザラート)」という野菜。
日本ではあまり知られていませんが、ドイツでは冬になるとサラダの定番として欠かせない存在です。
小さな緑の葉が特徴的で、ほんのりナッツのような風味があるこの野菜は、日本ではほとんど手に入らないので、ドイツで生活をしたことのある日本人にとっては恋しくなる存在です。
今回は、このフェルトザラートの魅力と、興味深い名前の話を中心にご紹介します。

ドイツで暮らしていると、スーパーや市場でよく見かける「Feldsalat(フェルトザラート)」という野菜。
日本ではあまり知られていませんが、ドイツでは冬になるとサラダの定番として欠かせない存在です。
小さな緑の葉が特徴的で、ほんのりナッツのような風味があるこの野菜は、日本ではほとんど手に入らないので、ドイツで生活をしたことのある日本人にとっては恋しくなる存在です。
今回は、このフェルトザラートの魅力と、興味深い名前の話を中心にご紹介します。

皆様は何年か前に「フランスの国民的炭酸」で話題になった「オランジーナ」(Orangina)をご存知でしょうか?
オランジーナとは1935年にスペインの薬剤師によって開発され、その後フランス人が販売権を購入して世界中に広めた炭酸入り清涼飲料のことで、フランスでは最も消費されているソフトドリンクのひとつとして有名です。
そして、2012年に日本でも販売が開始され、オランジーナは瞬く間に日本人の心を掴んで販売者の予想をはるかに超える大ヒット商品となったので、飲んだことがあるという方も少なくはないと思います。
そんな日本人の間でも人気なフランスの国民的炭酸ですが、実はスイスにもオランジーナに負けないぐらいの国民的炭酸と呼べる独自の飲み物が存在します。
スイスを訪れたことのある方ならこの事実を既に知っている可能性があるものの、現地に行ったことがなければ実物を目にする機会もないことから、大半の人にとっては初耳の筈です。
そこで、今回は読者の皆様にスイス国内の飲料事情についての知識を深めていただくために、スイスの国民的飲料をはじめ、スイスでしか味わえないおすすめ商品をご紹介させていただきます。

春から夏にかけて新緑が芽吹く山々では、山菜狩りをするのに絶好のシーズンですよね。
皆さんは山菜狩りに行かれますか?日本だと、ふきのとう、たらの芽、わらび等など、季節の山菜は食卓を美味しく、豊かにしてくれますよね。

私がドイツ人の夫と結婚して義理の母から教わった最初のドイツ菓子が、クリストシュトーレンでした。
彼女のお母さんが、その昔一流ホテルのレストランで料理人をしていたらしく、毎年12月になると当時のレシピでシュトーレンを焼くのが彼女のクリスマス前の習慣だったそう。
私も当時のクリストシュトーレンのレシピを教えてもらって、毎年クリスマス前にシュトーレンを焼くようになりました。今回は、我が家に伝わる秘伝のレシピを紹介したいと思います!

日本で生活していて、自身がスイス出身であることを明かすと、「景色が素晴らしい国」や「一度は行ってみたいところ」などスイスに対する憧れを述べる方が多いような印象を受けます。
確かにスイスは空気もキレイで他ではなかなか見ることのできないアルプスならではの大自然が広がってスイス人自らもその美しさに圧倒されるぐらいです。
そのため、旅行先としての人気も非常に高く、可能であればスイスに住みたいと思っている方も少なくはありません。
特に、アウトドアが好きだったり、山のアクティビティが趣味だったりする人にとってスイスはハイキングやウィンタースポーツを始め、パラグライダーからベースジャンピングまであらゆる形でその大自然を満喫できる楽園のような場所です。
しかし、スイスはアルプス山脈に面している内陸国と言う地理的条件やその環境から実はあまり知られていない様々な社会問題を抱えており、中には政府が積極的に対策を講じているほど深刻なものも存在します。
したがって、今回は実際に住んでみないとなかなか分からないスイスにおける生活上の問題についてご紹介したいと思います。
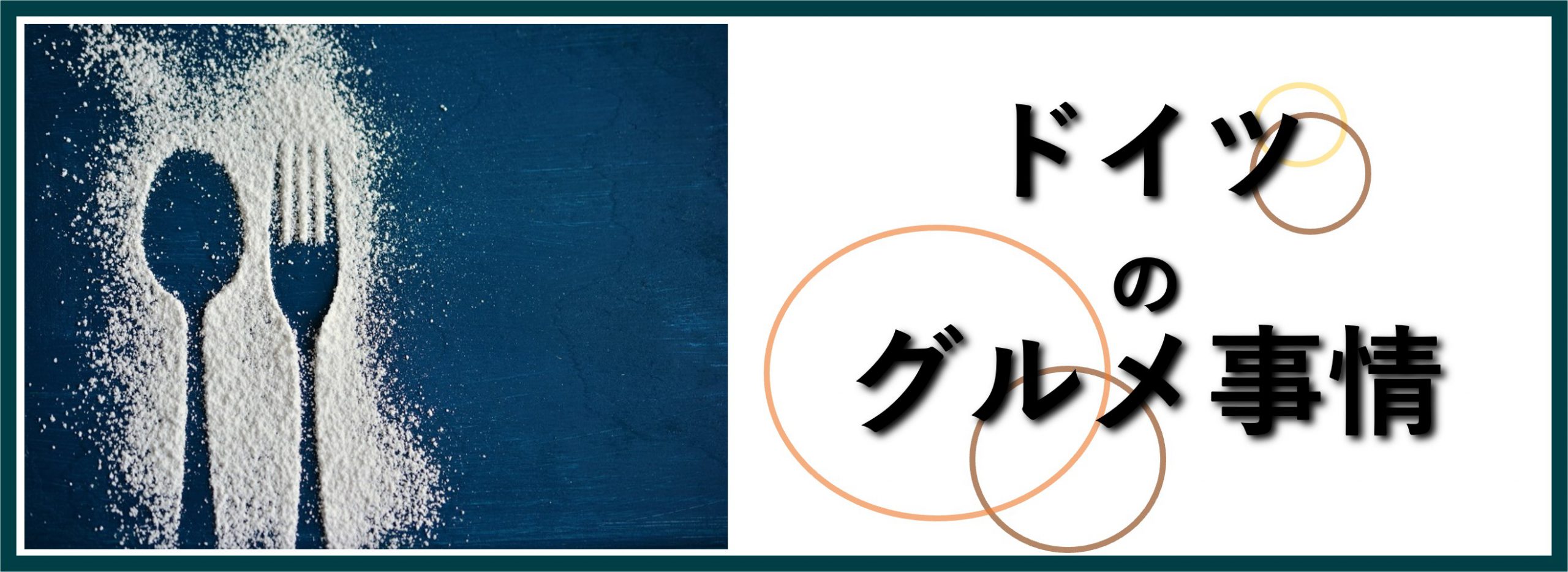

いきなりですが、皆様はスイス人の主食といえば何だと思いますか?
というのも、日本人は必ずと言っていいほどお米をメインの食材にして様々なおかずを添える習慣があり、主食と副食が明白になっているせいか、国外でも同様な概念があると考えているようです。
しかし、スイスを始め、欧米諸国ではそのような概念がないため、主食は何だと尋ねられた際にいつも困ってしまい、強いて言うなら「パン」もしくは「ジャガイモ」がそれに当たると答えるしかありません。
したがって、スイス人に対して主食は何であるかを尋ねた際に納得のいく回答を得るのはなかなか難しいです。
一方、スイス人なら誰しもが口を揃えて自身の「ソウルフード」と主張する食べ物なら存在します。
国外ではさほど有名でないものの、スイス人から見ればそれは「スイスの国民食」などと称されるほど絶大な人気を誇り、季節を問わずに色々なシチュエーションで食べられている食材です。
という訳で、今回は意外と知られていないスイス人のソウルフードである「セルヴェラ」をご紹介させていただきます。

12月に入ると、ドイツでは本格的にクリスマスの準備が始まります。
クリスマスは、ドイツ人にとって一年で最も大切な家族イベント。
おじいちゃん、おばあちゃん、子供や孫たち、普段は離れて暮らしている家族が集合して、久しぶりに家族水入らずで過ごす時間。まるで日本のお正月といった感じです。
そして日本でも住んでいる地域や家庭によってお正月にいただくおせち料理に違いがあるように、ドイツのクリスマス料理も地域や家庭ならではの特色があります。

過去に、ビールを注文する際にスイスとドイツで言い方が異なることに言及しましたが、これまでのスイスドイツ語講座をご愛読なさっている方であれば、飲み物にだけでなく、様々な分野において同様なケースが存在することにお気付きになっているかと思います。
もちろん、相手との意思疎通が可能であれば、細かい違いに困ることは基本的になく、自分が求めたものと全く別の品が出てくるのは非常に稀です。
しかし、スーパーなどでは必ずしも言葉が通じる相手がいるとは限らず、パッケージの記載や標識等のみを頼りにするしかありません。
つまり、コミュニケーションがそもそもできない場面では、結局、自分が欲しいものを諦めてしまうか、内容を把握していないまま直観に基づいて選択を行うことになります。
そのような出来事で未知との遭遇を体験するのも海外旅行の楽しみのひとつであるとの考え方がありますが、分からないものには一切手を出さないという慎重派であれば、時と場合によっては行動しにくくなってしまいます。
特に食事は取らない訳にはいきませんので、一定の知識を身に付けておいた方が断然得です。
したがって、今回はスイスでの腹ごしらえに困らないためにも、スイスドイツ語における食べ物の言い回しについて色々とご紹介させていただきます。

スイス人として日本で生活しているとあの人気アニメ「アルプスの少女ハイジ」を話題にされることが非常に多く、中でもアルムおんじが暖炉でチーズを溶かしてハイジに「ラクレット」(Raclette)を振る舞うシーンには大半の方が衝撃を受けたと度々お聞きします。その影響もあって、「私もラクレットを食べてみたい」と思っただけでなく、わざわざスイスを訪れてその目標を達成された人までいるそうです。
とはいえ、近頃は日本国内でラクレットを提供するお店が増えていることもあって、遠く離れた現地に足を運ばなくてもハイジと同じ体験ができるようになっています。
しかし、「ラクレット」の名前が付いているからといってそれが必ずしも本場スイスのラクレットと同じ料理であるとは限りません。
というのも、私自身も日本で何度かラクレットをいただいたことがありますが、アレンジレシピなどオリジナルとは少し違うものが出てきたケースが多かったので、少し残念な気持ちになったのが正直なところです。
また、ラクレットは誰でも容易に作れるチーズ料理と思われがちですが、食材、調理法、食べ方などが形式化された独自の食文化が存在するため、それらをある程度遵守しないとラクレットではなく、ただの焼きチーズになってしまいます。
そこで、スイス人としては日本の皆様にせめて正統派を知った上でアレンジバージョンを楽しんでいただきたいと強く思っておりますので、今回はアルプスの少女ハイジも愛したラクレットについて色々とお話しさせていただきます。