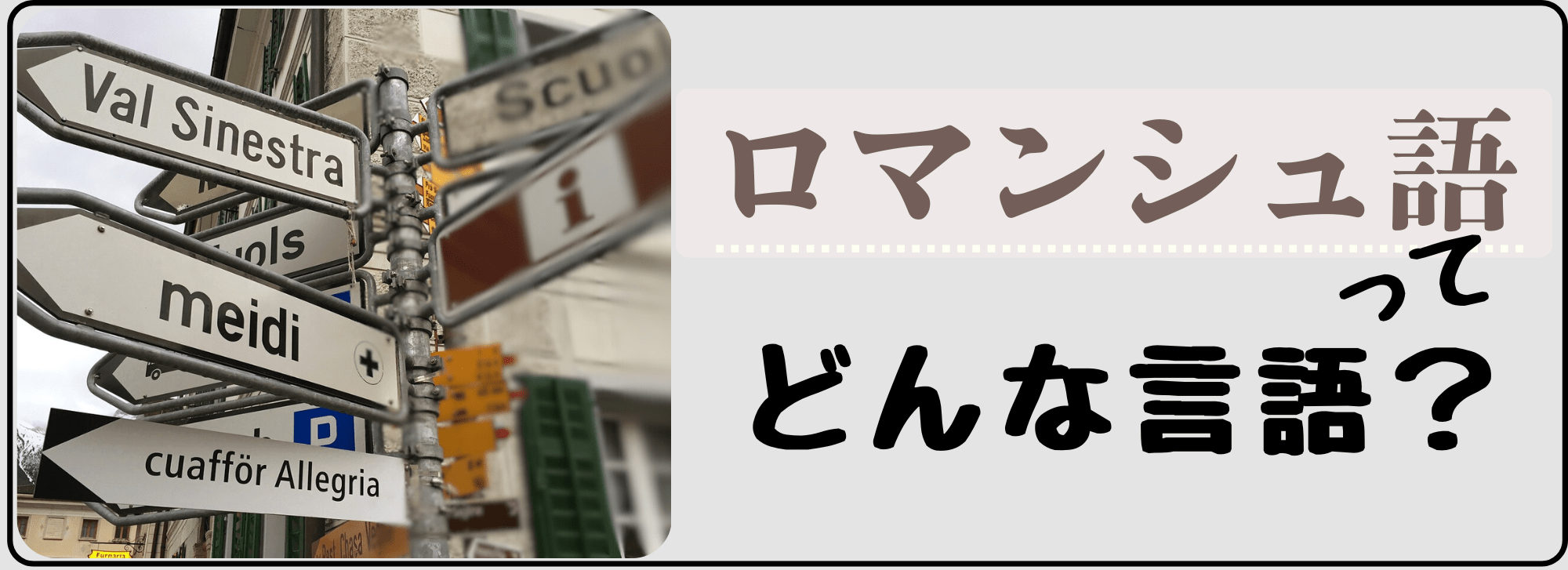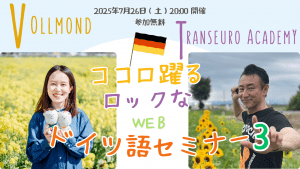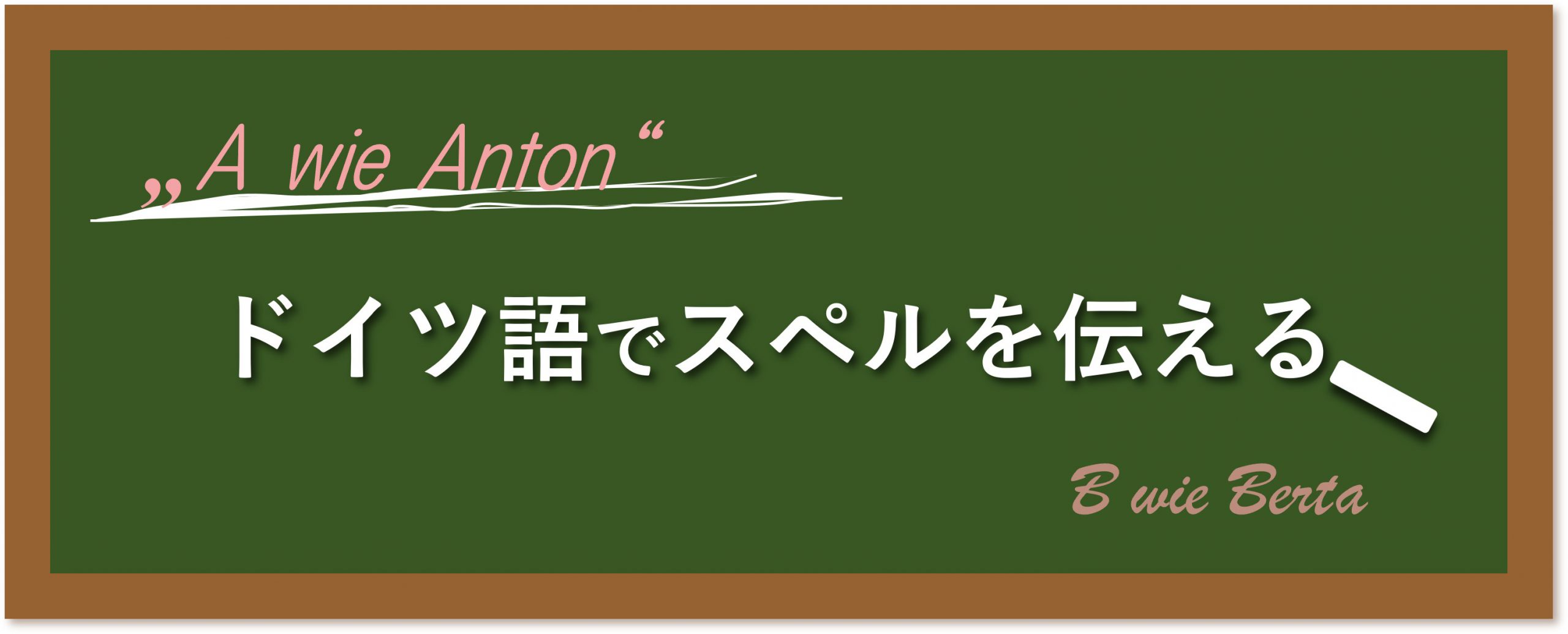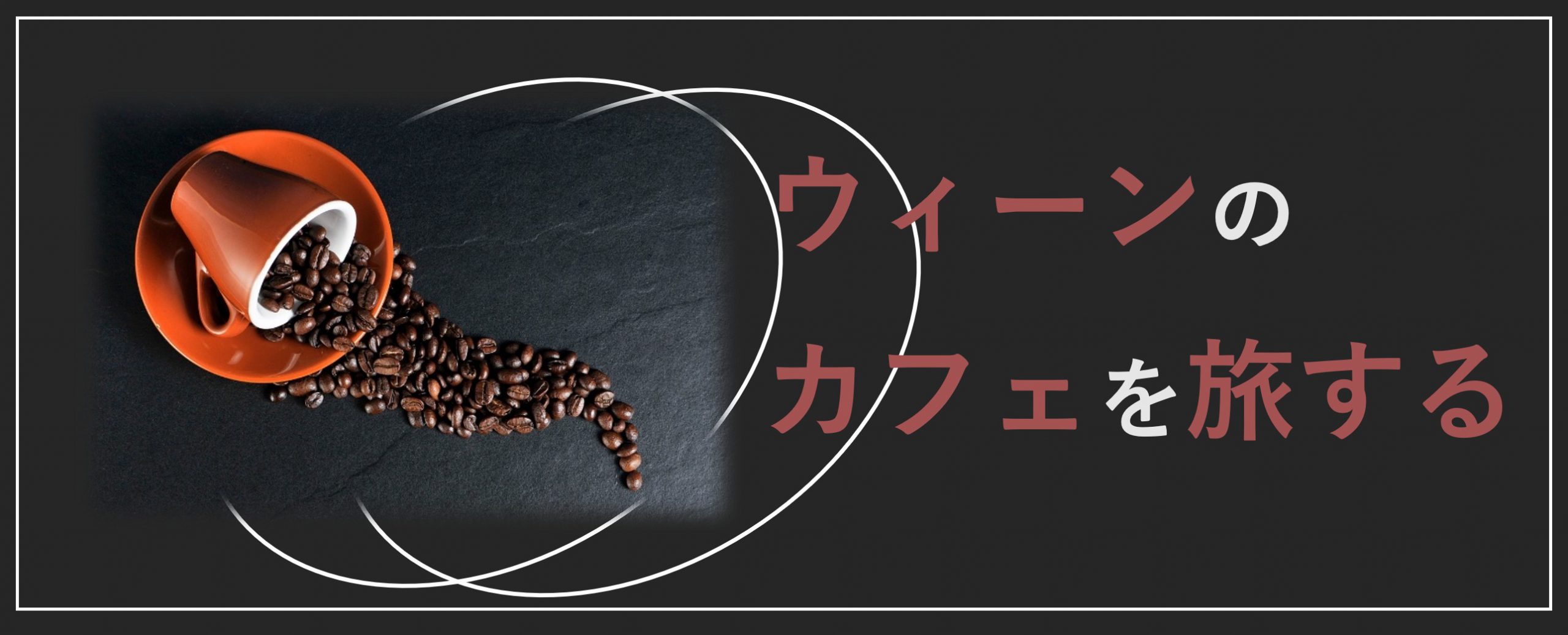今年もやります!VollmondとTEアカデミーの夢のコラボ! “ココロ躍るロックなWEBドイツ語セミナー 3” 2025 年 7 月 26 日(土) 開催 参加無料
~今年もVollmond代表のkomachiさんこと岡部美哉子さんをゲストに迎え、真夏の夜をドイツ語ネタで熱く盛り上げます!!~
今回のお題は『ドイツ語の好きなところ、嫌いなところ』!
昨年(2024)の夏からスタートしたトランスユーロ(TE)アカデミーとオンラインドイツ語スクール・Vollmondのコラボイベントですが、これまでTEアカデミーのオンラインセミナーや、Vollmondのポッドキャスト、ショート動画において、ドイツ語にまつわる様々なテーマを取り上げてきましたが、まだまだ両者のドイツ語ネタが尽きることはありません!
そこで、TEアカデミーでは昨夏に続いて2025年の夏もTEアカデミー+Vollmondのコラボイベント『ココロ躍るロックなドイツ語セミナー3』を開催することにしました!
もちろん、今回もコラボセミナーを担当するのは、ロック加藤ことトランスユーロ代表の加藤勇樹 と、KomachiさんことVollmond代表の岡部美哉子さん です。
この二人のコラボはもうすでに皆さんお馴染みになりつつあるかと思います。
ポッドキャストの収録時でも、放っておくと収録とは無関係に果てしなくドイツ語ネタで盛り上がっている二人ですので、もうほとんどドイツ語病に取り憑かれていると云っても過言ではありません。そんなドイツ語病の二人がいつものように様々なドイツ語ネタを繰り出して、この夏の夜を熱く盛り上げます!
今回のセミナーのお題は『ドイツ語の好きなところ、嫌いなところ
ドイツの語の好きなところはよく聞きますが、嫌いなところってあまり聞かないですよね? まずはこの二人からそれぞれドイツ語の好きなところ、嫌いなところを挙げてもらいましょう。
そして、セミナー参加者の皆さんからも是非皆さんにとっての「ドイツ語の好きなところ、嫌いなところ」を聞かせてください!!
申し込みの際に皆さんに事前に書き込んでいただいて、本番でお二人からチョイスして紹介させていただきます。そしてお二人からそれぞれ激アツなコメントをもらいますので、どんな話に転んでいくか楽しみですね!☆
2024年 広島県尾道のスタジオでのKomachiさんのポッドキャスト収録風景
2025年の夏も是非ご一緒にロックな夢の共演にココロ躍らせてみませんか?
【詳細】
開催日 2025年 7月 26日(土)
時間 20:00(日本時間)開演 (公演時間は約1時間を予定、最後に質疑応答あり)
セミナー形式 Zoomによるライブ配信(会場の臨場感を出すためにできるだけカメラオンでお願いします)
講師 加藤 勇樹 (トランスユーロ株式会社 代表)
ゲスト 岡部 美哉子 (Vollmond株式会社 代表)
申込み締切り 2025年7月22日(火)
参加希望の方は以下のフォームからお申し込みください。
お申し込みの際・・・
■岡部代表と加藤に聞いてみたいこと、二人へのメッセージも募集します!
それでは皆さんのご参加お待ちしております!
Kostenloser Online-Seminar von Herrn Yuki Kato
Frau Miyako Okabe, Geschäftsführerin von Vollmond, zu Gast am rockin‘ Seminar
Datum Samstag, 26. Juli 2025
Uhrzeit 20.00 -21.00 JST
Seminarsform Online per Zoom
Lehrer Yuki Kato (CEO von transeuro, inc.)
Gast Frau Miyako Okabe (Geschäftsführerin der Online-Deutschschule Vollmond )
Kosten Frei (Voranmeldung ist erforderlich)
Veranstaltungssprache Japanisch
Anmeldung Anmeldeformular
Anmeldefrist 22. Juli 2025
Eine Anmeldung ist ab sofort unter (お申し込みフォーム – トランスユーロアカデミー (trans-euro.jp) ) möglich, aber bitte unter Nennung Ihres Namens, Ihres Berufs und Wohnorts, wobei es uns sehr freuen würde, wenn Sie mitschreiben, was Ihnen an der deutschen Sprache gefällt, und was nicht .
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.