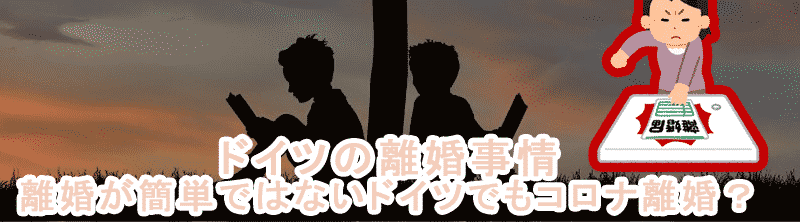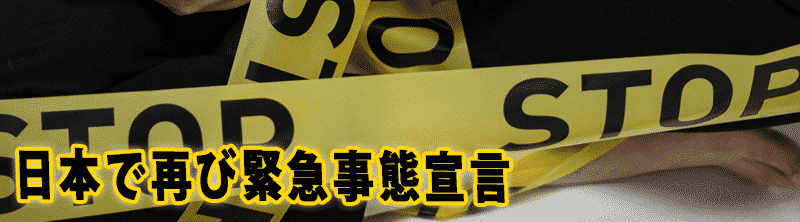チョコレート大国スイス
目次
皆様はスイスの特産品と言えば何を思い浮かべますか?
私の経験上、この質問に対して日本人の多くは時計と回答しますが、それ以外の国ではスイスの特産品として最初に挙げられるのがチョコレートだそうです。
私もその点につきましてはスイス人として「なるほどね」と思うほど納得しますし、日本での生活で一番恋しくなるのもやっぱりスイスチョコです。
その年間輸出量からベルギーがチョコレートの国と思われがちですが、実はスイスがそれ以上のチョコ大国であることをご理解していただくためにも、今回はスイスチョコについてご紹介させていただきたいと思います。