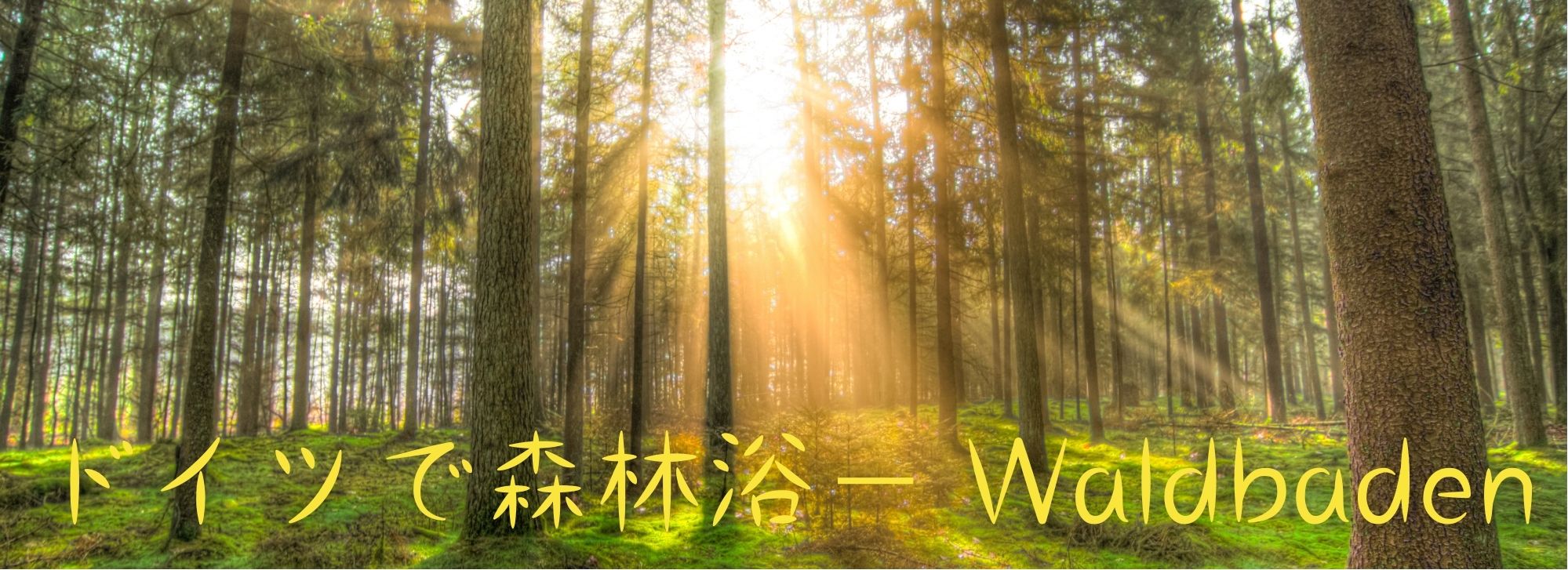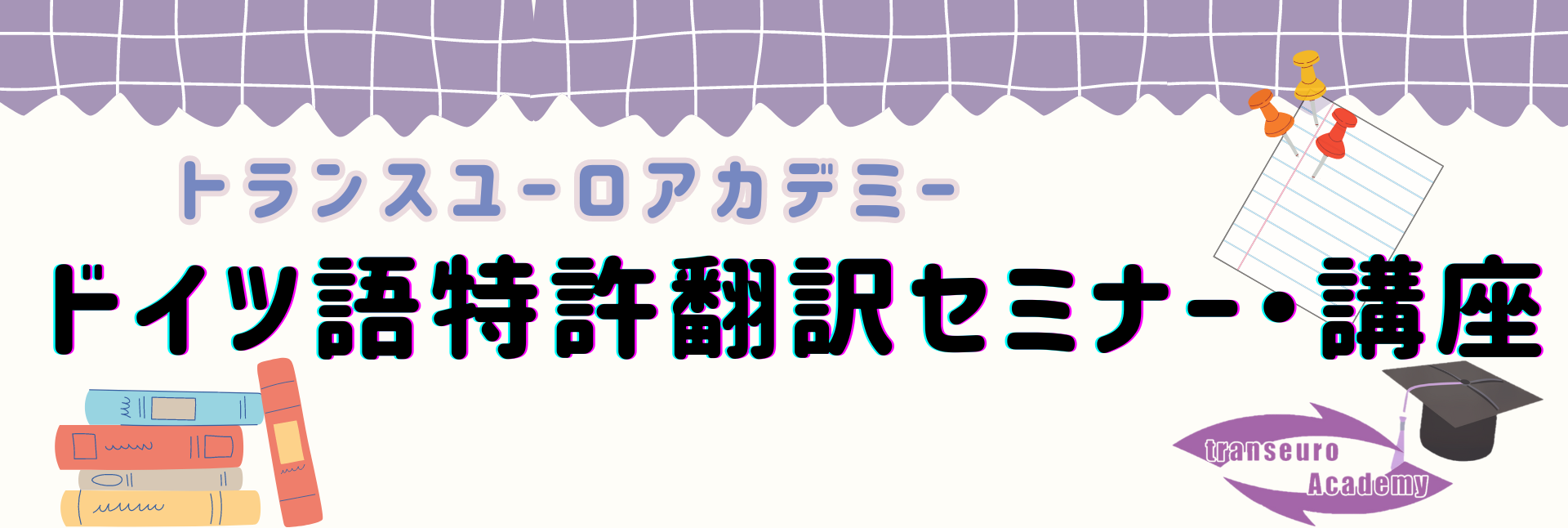*本講座は満員御礼のため、お申込み受付を終了いたしました
このたび入門コースに続く形で一般コースの開講を決定しました!今回は、比較的易しいテキストを使って一般コースを開催します!!
2025年12月に終了した入門コース(第8期)ですが、いつもと同様に満席となりました。
この入門コースには、複数のプロの特許翻訳者さんを始め、ドイツ、オーストリアにお住まいの人、現役の大学生さんや大学院生さん、そしてドイツ語学習歴のある社会人さんなど、世代や職業を越えて国内外から多くの方々が参加してくれました。
皆さん徐々に特許翻訳の魅力に引き込まれたご様子で、とても熱いクラスになりました。
なので、この勢いに乗って、すぐに一般コースをスタートさせたいと思います!!
▶早速申し込む
2026年2月スタート!WEBドイツ語特許翻訳講座(一般 第8期)の開講が決定!

講師は、引き続き、トランスユーロのロックな会長・加藤勇樹が担当いたします。
加藤は最近ではカフェやドイツフェスティバルにてワークショップを開催したり、上智大学にて講演を行なったりと、その活動の幅をますます広げております。
今回も、きっとまたロックなドイツ語特許翻訳の世界を皆様にご案内できると確信しています。継続受講の方はもちろん、受講再開される方も大歓迎いたします。
*一般講座の新規受講については、トランスユーロアカデミー入門講座を修了した方、または同入門講座修了程度のスキル(特許翻訳の基礎知識があり、ドイツ語力が独検準1級以上)をお持ちの方がお申込み可能です。受け入れ可否につきましてはアカデミー事務局までご相談ください。
 上智大学ヨーロッパ研究所の招きで講演
上智大学ヨーロッパ研究所の招きで講演
ドイツ語特許翻訳講座の一般コースは繰り返し受講してスキルアップをしていただく仕組みになっておりますので、中級・上級といった括りはありません。
しかも受講を重ねるごとに受講料が減免される制度になっており、つまりは、上達するにつれて受講料がお得になります。上級クラスに行けばいくほど受講料が高くなるのが一般的な語学スクールだと思いますが、トランスユーロアカデミーは頑張る人を応援したいと思っているためこのような制度を導入しています。
講座+講師による個別の添削指導
毎回の講座前に予習(任意)を提出していただいた方には、講師が個別に添削しフィードバックします。
予習 → 添削 → 復習 → <講座> → 復習・・・・
と繰り返すことで、着々と実力が上がります。
この学習の仕組みは、トランスユーロアカデミーの特徴の1つです。
翻訳力+技術知識を得る
一般コースでは、全8回の講座を通して1つの特許明細書を翻訳していきます。1つの明細書に腰を据えて取り組むことで、必要な翻訳技術を学べるだけではなく、技術内容の理解も深めることができます。
明細書の一部分を抜粋したようなテキストでは味わえない、「特許翻訳の醍醐味」を感じていただけるはずです。
講師からのメッセージ
今回は入門コースに続いてすぐに一般コースを開講します。
入門コースから続いて受講される人は、まだまだ特許翻訳には不慣れですので、今回の一般コースでは内燃機関などの技術的難度の高いテキストは避け、皆さんの生活に身近なものを扱った比較的易しい特許明細書をテキストとして選びます。
特許翻訳に興味はあるのだけど、難しい技術は苦手、という特許翻訳初心者の方々にとってはもってこいのテキストですので、皆さんバックグラウンドは全然違っていても、ドイツ語大好きな人であれば、どなたでもご一緒にお楽しみいただける講座となります。
是非ご参加ください!
Gleich und Gleich gesellt sich gern
oder
Gegensätze ziehen sich an ?

講座の開講日程は以下の通りです。
| 開講日 |
2/13・2/27・3/13・3/27・4/10・4/24・5/8・5/22(隔週金曜日・全8日) |
| 時間 |
19:30~21:00 (日本時間)90分 |
| 場所 |
Zoomを使用したオンライン開催 |
| 受講料 |
60,000円 (大学生・院生 20,000円) |
| 定員 |
10名(最少開講人数に達しない場合は中止となります) |
| 講師 |
加藤勇樹 |
| 使用予定テキスト |
ドイツ語特許明細書
キーワード:「Wurst mit Senf oder Ketchup」
(テキストは場合によっては変更する可能性があります) |
| お申込み |
★申し込みフォーム |
| お問合せ |
info@trans-euro.jp |
一般コース受講2回目以降 受講料の割引あり!
- 2回目 5000円割引
- 3回目 10000円割引
- 4回目 15000円割引
- 5回目以降 20000円割引
- 全8日の講座の途中から受講する場合は適用されません
- 以上の回数のカウントに入門講座は含まれません
*大学生・院生の方の受講料は2022年より「入門コース10000円」、「一般コース20000円」に値下げしましたので上記回数割引の対象外となりました。
*日独協会会員様の割引制度は終了いたしました。

.jpg)