メルヘン それはドイツから
目次
赤ずきん、ヘンゼルとグレーテル、ブレーメンの音楽隊。。。子供時代に慣れ親しんだ物語の数々ではないでしょうか。このような物語、いわゆるメルヘンと聞いてどのようなイメージが浮かびますか?夢のようなおとぎ話、森の中に住む魔女、ヨーロッパのふるいお話など様々なイメージがあるかと思います。これらは主にドイツの民話であり、古くから伝えられている物語です。ドイツの観光ツアーにおいては、メルヘン街道というものもありますね。今回はこのメルヘンについてお届けします。

目次
赤ずきん、ヘンゼルとグレーテル、ブレーメンの音楽隊。。。子供時代に慣れ親しんだ物語の数々ではないでしょうか。このような物語、いわゆるメルヘンと聞いてどのようなイメージが浮かびますか?夢のようなおとぎ話、森の中に住む魔女、ヨーロッパのふるいお話など様々なイメージがあるかと思います。これらは主にドイツの民話であり、古くから伝えられている物語です。ドイツの観光ツアーにおいては、メルヘン街道というものもありますね。今回はこのメルヘンについてお届けします。
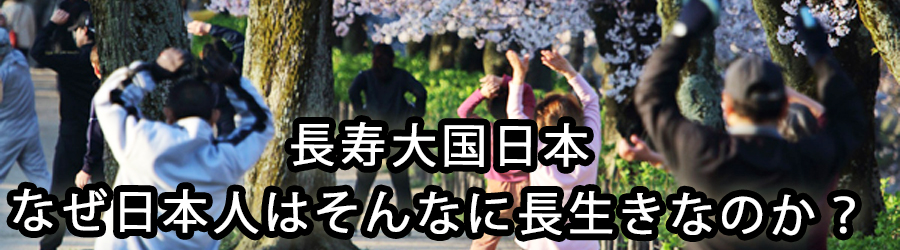
目次
日本の平均寿命は84.2歳と、ドイツの平均寿命80.6歳よりも高くなっています。沖縄県の女性の平均寿命はさらに高く、86歳です。長寿の理由は一体どこにあるのでしょうか?日本人の遺伝子か、日本の健康保険制度か、あるいは生活習慣でしょうか?
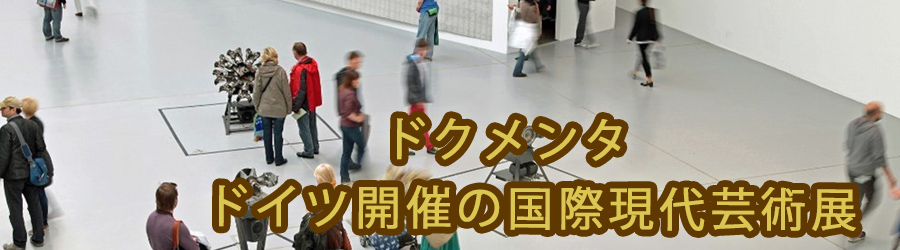
目次
芸術の都といえばパリ。音楽の都といえばウィーン。しかし今日ではそのような認識も徐々にアップデートされている現状があるのではないでしょうか。ドイツでは、5年に一度、カッセルでドクメンタという世界最大規模の国際現代芸術展が行われています。会期中には、人口20万人の都市であるこのカッセルに欧州全土から約60万人の観客が集まるほどです。今回は芸術の祭典となるこのドクメンタについてお伝えします。

目次
オーストリアの学校では9月から新学期が始まりました。私は子どもの頃からこの時期がとても好きでした。季節が変わり、友人にまた会えて新しいノートとペンを買って、何か新しい事が始まるみたいなワクワクする気持ちが湧いてきます。日本の子どもたちも4月には、こんな気持ちになりますか?各国による学校教育制度には意外と大きな違いがあり、オーストリアと日本もそうなので、今回はオーストリアの教育制度をご紹介します。
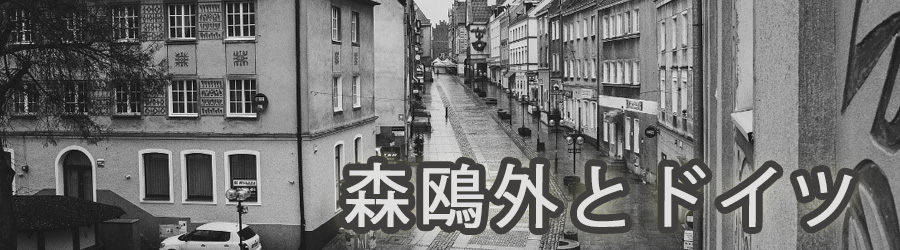

目次
今まで何度かにわたり、スイスの名所をご紹介させていただきましたが、それらは何れもスイスを代表する、言わば定番の都市ばかりでした。
しかし、観光ツアーにまず含まれることがなく、ガイドブックに掲載されることも稀でありながら、実は他のどの都市よりもスイスを代表する場所が存在します。
それがシュヴィーツなのです。
スイスを訪れたことのある方であってもその名前を聞いたことがないという人が多いことでしょう。したがって、今回はそのシュヴィーツについてのお話をさせていただきます。

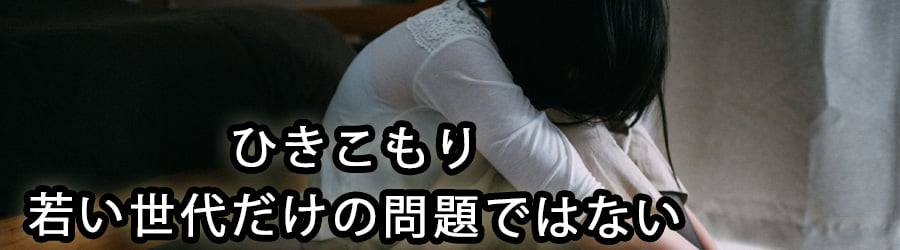
目次
ひきこもりとは、社会参加せず、自宅や自室からほとんど出てこなくなる現象と、これに該当する人のことを指します。多くは既に学生時代からひきこもりを始め、家から出なくなり、大人になっても親の家に住み続けています。きっかけは多岐にわたりますが、例えば、学校でのいじめや日本の教育制度における成績至上主義よる多大なストレスなどがあります。
目次
トランスユーロアカデミーの人気講座「ドイツ語特許翻訳講座」の開講に先立ち、2021年9月25日、「そもそもドイツ語の特許翻訳とは何なのか?」といった初歩的な疑問を解消するロックなセミナーが開催されました。

目次
ドイツの美術について、中世、近代とお伝えしてきました。今回は20世紀初頭から現代にわたるドイツの美術についてお伝えします。ドイツ美術が、西洋美術史の中で最もスポットライトを浴びるのは、19世紀末から20世紀初頭ではないでしょうか。なかでもドイツを発祥とした表現主義は、その後に起こった様々な芸術運動への影響も多大です。世界大戦という混乱期のドイツ美術には、比類なき激動的な芸術家のパッションがあったようです。